おはようから、おやすみまで わいざーと申します🎵
突然ですが、「あれ、なんでこんなもの買っちゃったんだろう…」と後悔したこと、ありませんか?

冷静に考えたら必要なかったのに、
その場の空気や雰囲気に流されて、つい財布を開いてしまった――。
それ、あなたのせいではありません。
人間の脳は、もともと“非合理的”にできているんです。
今回は、そんな“ちょっと不思議な私たちの行動”を読み解く学問、
行動経済学の基本をやさしく解説します。
そもそも「行動経済学」って何?
行動経済学とは、
「人は必ずしも合理的に判断・行動しない」
という前提に立って、人間の“ちょっと変な”行動パターンを研究する学問です。
これまでの経済学(伝統的経済学)はこう考えていました。
人は常に合理的で、自分の利益を最大化する行動をとる
でも現実の私たちはどうでしょう?
- コンビニで買うつもりのなかったお菓子をついカゴに入れる
- セールの文字に弱くて、結局無駄遣いしてしまう
- やらなきゃいけないことを先延ばしにする
……全然“合理的”じゃないですよね?笑
この人間らしい矛盾やバイアス(思い込み)を科学的に研究し、
社会やビジネス、教育などにも活かそうとするのが、行動経済学なんです。
人間の判断は「ヒューリスティック」でできている
行動経済学では、人が合理的な計算をせずに意思決定をする「近道」のような思考法を
ヒューリスティックと呼びます。
たとえば…
- 「なんとなくこっちのほうが良さそう」
- 「あの人が言ってたから信用できそう」
- 「前にも買ったから、今回も大丈夫そう」
これは“直感”とも似ていますが、厳密には過去の経験や感情に基づく省エネな判断なんですね。
でもこのヒューリスティックが、
ときに間違った判断や思い込みを引き起こす元にもなるのです。
有名な実験:ジャムと選択のパラドックス
行動経済学の有名な実験のひとつに、
「ジャム売り場の実験」があります。
2つのグループに分けて試したところ、
- 6種類のジャムを並べた場合…試食後の購入率は約30%
- 24種類のジャムを並べた場合…購入率はわずか3%
選択肢が多すぎると、かえって人は選べなくなる――
これを「選択のパラドックス」といいます。
この実験からもわかるように、人は情報が増えると判断力が鈍るという特徴があるのです。
関連リンク・参考資料
■ 行動経済学とは?国や自治体も注目する新しい経済学
「行動経済学とは? 国や自治体も注目する新しい経済学について知る」
[日経ビジネス]
▶︎ https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00081/070800222/
■ バリー・シュワルツ:選択のパラドックス(TED Talk)
「バリー・シュワルツ: 選択のパラドックスについて」
“選べる自由”が、むしろ人を不幸にすることもある――
行動経済学の代表的なテーマをわかりやすく解説するTED講演
▶︎ https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_the_paradox_of_choice?language=ja
行動経済学が教えてくれること
この学問が面白いのは、
「自分の行動には“見えない仕掛け”がある」と気づかせてくれる点にあります。
- 人は感情に流される
- 損をしたくないと思うと判断が狂う
- 他人の行動を真似たくなる
これらはすべて、誰にでもある“心のクセ”なんです。
行動経済学は、そんなクセを「悪いもの」として否定するのではなく、
「自分で気づき、うまく付き合っていこう」という知恵の学問なんですね。
まとめ:合理的じゃなくていい。でも、気づいていたい
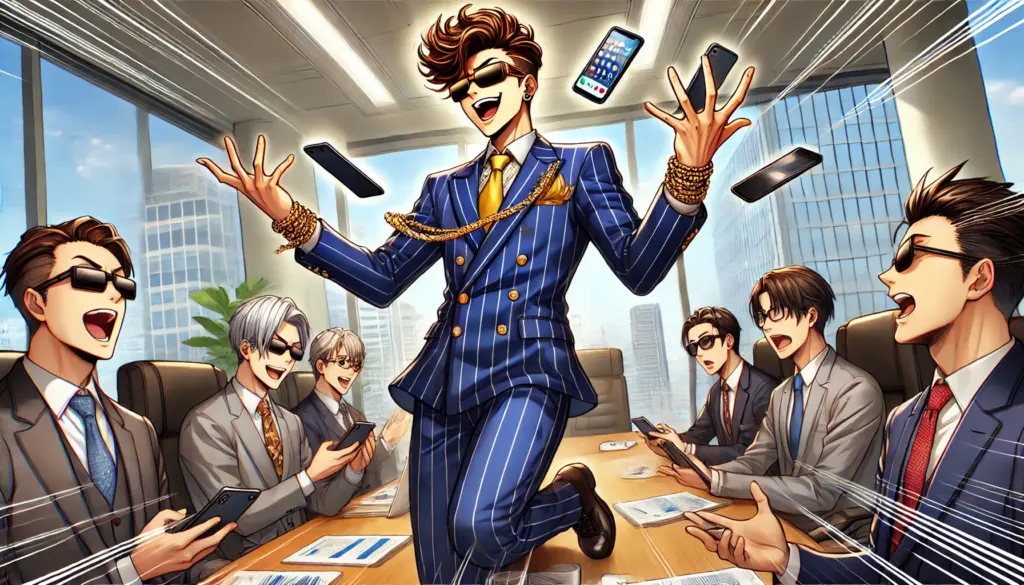
人間は、もともと非合理。
それでも、行動経済学の視点を持つことで、
「なぜ自分はそう動いてしまったのか?」と振り返る力がついていきます。
そしてそれこそが、
情報に振り回されず、自分で選べる人になる第一歩かもしれません。
次回は、「損をしたくない!」という人間の本能が引き起こす、
プロスペクト理論と損失回避の心理についてお話しします!
では、また次の記事でお会いしましょう!
グッモグッナイグッラック!!
▼行動経済学シリーズまとめ
- 第1回:人は合理的に行動しない?行動経済学の基本(このページ)
- 第2回:つい買ってしまうのはなぜ?損失回避とプロスペクト理論(近日公開)
- 第3回:選択肢が増えると迷う?選択のパラドックス
- 第4回:なぜ高い方を選んでしまう?アンカリング効果の正体
- 第5回:みんながやってるから?社会的証明の心理
- 第6回:無料に弱いのはなぜ?ゼロ価格効果と心理的コスト
- 第7回:行動経済学を日常に活かすために



コメント