おはようから、おやすみまで、わいざーと申します🎵
突然ですが、「やりたいことある?」って聞かれると、ちょっとモヤっとしませんか?
SNSでは「夢に向かって努力してる人」が目に入るし、自己啓発本を開けば「情熱を持て」「やりたいことを見つけろ」といった言葉が並んでいます。
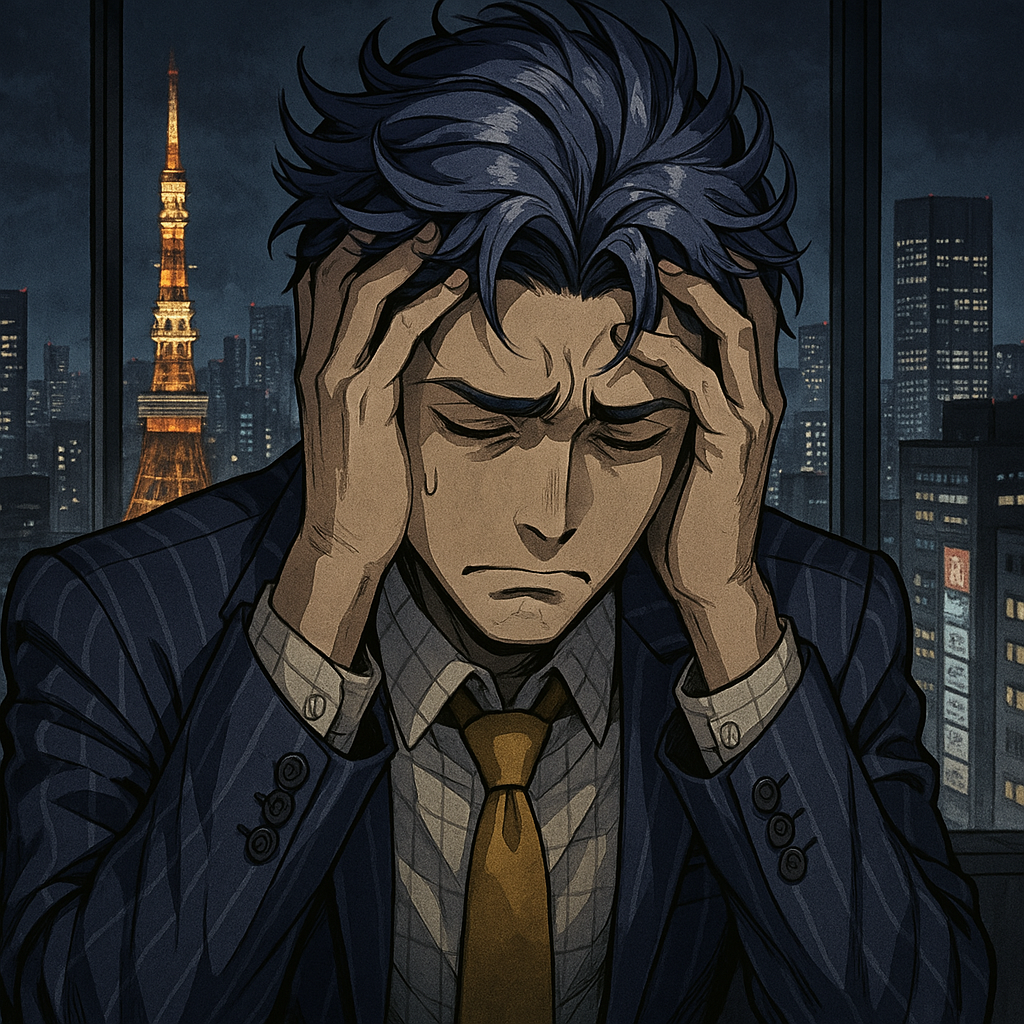
でも、正直なところ──
「そんなに簡単に“やりたいこと”って見つかる?」
という疑問を抱えている人、少なくないと思うんです。
夢がない=劣っている?という誤解
「何かに打ち込んでる人」って、すごく輝いて見えるし、憧れますよね。
でも一方で、「自分にはまだそういうものがない」というだけで、“遅れてる”とか“劣ってる”みたいに感じてしまう空気もある。
これは、社会全体にある「夢を持つのが当たり前」という同調圧力が原因かもしれません。
心理学的には“普通のこと”なんです
実は、「やりたいことが分からない」という状態、心理学ではごく自然なものとされています。
たとえば、自己決定理論(Self-Determination Theory)では、人間のモチベーションは以下の3つの要素に支えられているとされます。
- 自律性(自分で選んでいる感覚)
- 有能感(できるようになっている実感)
- 関係性(誰かとのつながり)
この3つが揃って初めて、「内発的動機づけ=やりたいこと」が湧いてくる。逆に言えば、焦って外から探そうとしても、ピンとこないのは当たり前なんです。
UCLAの学生も“迷っている”
アメリカのUCLAが行った学生意識調査では、「将来の目標が明確でない」と答えた学生が約60%に上りました。
つまり、あの有名大学の学生たちでさえ、キャリアや人生の方向性に迷っているということ。
それを知ったとき、僕はちょっとホッとしたんです。「あ、自分だけじゃないんだな」って。
“やりたいことがない”は、むしろ余白であり可能性
僕は最近、「やりたいことがまだ分からない」という状態を、“未定”ではなく“未発見”と捉えるようになりました。
未来の可能性に開かれている証拠。
そして、自分の感覚にちゃんと耳をすませているからこそ、簡単に飛びつかない。
それって、むしろ健全なんじゃないかと。
焦らず、自分との対話を続けよう
「なんとなく面白そう」「ちょっと気になる」
そういった小さな興味をたどっていくことが、後々「やりたいこと」に育っていくこともあります。
大切なのは、焦らず、比べず、自分とゆるやかに対話していく姿勢。
今はその途中でOK。誰かと違っていても、何も問題ないんです。
次回予告:「迷ってる時間こそ、自分を育てている」
シリーズ第2回では、「キャリア選択=決断」ではなく「探索」であるという視点から、迷いの時間の意味を深掘りしていきます!
では、また次の記事でお会いしましょう!
グッモグッナイグッラック!!
参考リンク
シリーズリンク
- (次回)第2回「迷ってる時間こそ、自分を育てている」(※公開後リンク追加)


コメント